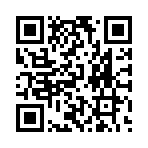2008年03月10日
モノづくりの未来・・・3
高性能を売りにしながら
世界的にシェアを拡大した会社とは・・・
それは、韓国のサムスンです。
実は韓国も日本と同様に3Gに移行しているのですが、
世界シェアの中では第2位のサムスン、第5位のLGと
トップファイブに入っています。
では、なぜ日本と韓国とでこの差が生まれたのでしょうか?
日本企業とサムスンの明暗を分けた差とは?
それは一言で言ってしまうと「戦略」に尽きてしまうかもしれません。
サムスンの海外進出はアメリカから始まりました。
戦略の要は『ブランドイメージの向上』
1996年のNYのタイムズスクエアー
世界一値段が高い野外広告として名高い
そして最も目立つ位置にサムスンは広告を出していました。
しかしながらバブルがはじける直前の1990年には
サムスンが広告を出している場所にSNOY
その近くにはCANON, AIWA, PANASONIC,
JVC,KIRINBEERと日本の名だたる企業が広告を出していました。
ここから分かることとは・・・
現在の日本の携帯市場を見てもわかるように
日本は確かに技術という点では世界的に圧倒的な力を持っています。
しかしその技術を使ってどうやって世界のマーケットを拡大していくかという
戦略的なところが欠けてきて弱くなってきている。
つまり高い技術力だけでは世界と渡り合えない状況に陥っています。
しかもその高い技術力すら、新たな危機に瀕しています。
実は1月下旬にサムスングループが新潟県にある
日本最古のステンレス加工メーカーの買収をしました。
経済新聞にも小さな記事ですが掲載されました。
なぜサムスンはこの会社を買収したのでしょうか?
日本には昔から職人と呼ばれ自分の仕事に誇りと
けして妥協しない姿勢を貫く方々がいます。
ステンレス加工も高度な技術が必要になります。
温度による変化が激しいため溶接の工程一つをとっても
熟練の技を持った職人さんたちが頼りとなります。
こうした長い時間をかけて育った日本の技術こそ
買収の狙いだったとみられています。
また他の高い技術力を持っている企業にも
海外からの業務提携のオファーが来ているそうです。
つまり日本の技術力はとても高く評価されているにもかかわらず
国内ではそれを活かしきれていないということになりませんか?
近い将来、日本でもサムスンやノキアなどの携帯を
使っている人を見かけることが多くなるかも。
そうするとメイドインジャパンは・・・
隠れてしまうでしょう・・・箱の中に。
世界的にシェアを拡大した会社とは・・・
それは、韓国のサムスンです。
実は韓国も日本と同様に3Gに移行しているのですが、
世界シェアの中では第2位のサムスン、第5位のLGと
トップファイブに入っています。
では、なぜ日本と韓国とでこの差が生まれたのでしょうか?
日本企業とサムスンの明暗を分けた差とは?
それは一言で言ってしまうと「戦略」に尽きてしまうかもしれません。
サムスンの海外進出はアメリカから始まりました。
戦略の要は『ブランドイメージの向上』
1996年のNYのタイムズスクエアー
世界一値段が高い野外広告として名高い
そして最も目立つ位置にサムスンは広告を出していました。
しかしながらバブルがはじける直前の1990年には
サムスンが広告を出している場所にSNOY
その近くにはCANON, AIWA, PANASONIC,
JVC,KIRINBEERと日本の名だたる企業が広告を出していました。
ここから分かることとは・・・
現在の日本の携帯市場を見てもわかるように
日本は確かに技術という点では世界的に圧倒的な力を持っています。
しかしその技術を使ってどうやって世界のマーケットを拡大していくかという
戦略的なところが欠けてきて弱くなってきている。
つまり高い技術力だけでは世界と渡り合えない状況に陥っています。
しかもその高い技術力すら、新たな危機に瀕しています。
実は1月下旬にサムスングループが新潟県にある
日本最古のステンレス加工メーカーの買収をしました。
経済新聞にも小さな記事ですが掲載されました。
なぜサムスンはこの会社を買収したのでしょうか?
日本には昔から職人と呼ばれ自分の仕事に誇りと
けして妥協しない姿勢を貫く方々がいます。
ステンレス加工も高度な技術が必要になります。
温度による変化が激しいため溶接の工程一つをとっても
熟練の技を持った職人さんたちが頼りとなります。
こうした長い時間をかけて育った日本の技術こそ
買収の狙いだったとみられています。
また他の高い技術力を持っている企業にも
海外からの業務提携のオファーが来ているそうです。
つまり日本の技術力はとても高く評価されているにもかかわらず
国内ではそれを活かしきれていないということになりませんか?
近い将来、日本でもサムスンやノキアなどの携帯を
使っている人を見かけることが多くなるかも。
そうするとメイドインジャパンは・・・
隠れてしまうでしょう・・・箱の中に。
2008年03月07日
モノづくりの未来・・・2
前回の続きから・・・
日本製の携帯電話は世界的に見ても非常に高性能&ハイスペック
しかしながら世界的シェアは全体の2%にも満たない現実。
その答えを紐解くには日本での携帯電話の
歴史を辿ることによって分かってきます。
自動車電話から始まった日本の携帯電話は、アナログから
第二次世代(2G)と呼ばれるデジタル方式に進化しました。
メールやインターネット接続も可能になりましたが・・・
これが誤算の始まりになります。
実は1993年に採用した2GのPDCという方式は
日本のみが採用した規格で、世界210以上の国と地域では
欧州で開発されたGSM規格が主流となっていました。
このPDCとGSMというシステムの違いが、
日本メーカーの海外進出を阻んだのです。
たらればですが、もし日本が2Gで、GSM方式を採用していたら
現在の世界シェアの状況は大きく変わっていたかもしれません。
そこで日本が次の手として何をしたかというと・・・
現在皆さんも使っている第3世代(3G)に
早々と移行し巻き返しをはかろうと試みます。
なぜなら世界共通のWCDMA/TDMA方式を3Gに採用したからです。
しかしながら、ここでも誤算がでてきます。
世界の7割以上が未だに2GのGSM方式を使用しているので、
3Gが主流の日本製の携帯電話は一向にシェア拡大することが出来ません。
ちなみにノキアは第二世代の廉価版を今も販売しています。
世界市場でいうと簡単な機能だけがついている携帯電話を
買ってくれる人の方が数は多いからです。
2006年にノキアは南アフリカに進出しました。
まずは廉価版の販売に力をいれ、値段の安い携帯を売ることによって
世界シェアナンバーワンの座を不動のものにしています。
ではなぜ日本では廉価版を販売しないのか?という疑問がでてきます。
日本の携帯電話の特徴は
キャリアと呼ばれる移動通信会社(NTTやSBなど)による
独特の販売方法によります。
メーカーはキャリアの要望に応じて商品を生産
それが各キャリアのブランドごとに販売されています。
これまでキャリアは競うように、メーカに機能の向上を求めてきていました。
つまり、日本向けの商品をつくるのに精一杯で
海外向けの商品をつくる余力が会社としてないというのが
どこのメーカーも抱えている問題になっています。
しかしながら高性能を売りにしながら
世界的にシェアを拡大した会社が存在します。
さあ、それはどこでしょう?
そしてなぜでしょう?
その話は次回に・・・(引っぱりすぎですかねぇ~)
日本製の携帯電話は世界的に見ても非常に高性能&ハイスペック
しかしながら世界的シェアは全体の2%にも満たない現実。
その答えを紐解くには日本での携帯電話の
歴史を辿ることによって分かってきます。
自動車電話から始まった日本の携帯電話は、アナログから
第二次世代(2G)と呼ばれるデジタル方式に進化しました。
メールやインターネット接続も可能になりましたが・・・
これが誤算の始まりになります。
実は1993年に採用した2GのPDCという方式は
日本のみが採用した規格で、世界210以上の国と地域では
欧州で開発されたGSM規格が主流となっていました。
このPDCとGSMというシステムの違いが、
日本メーカーの海外進出を阻んだのです。
たらればですが、もし日本が2Gで、GSM方式を採用していたら
現在の世界シェアの状況は大きく変わっていたかもしれません。
そこで日本が次の手として何をしたかというと・・・
現在皆さんも使っている第3世代(3G)に
早々と移行し巻き返しをはかろうと試みます。
なぜなら世界共通のWCDMA/TDMA方式を3Gに採用したからです。
しかしながら、ここでも誤算がでてきます。
世界の7割以上が未だに2GのGSM方式を使用しているので、
3Gが主流の日本製の携帯電話は一向にシェア拡大することが出来ません。
ちなみにノキアは第二世代の廉価版を今も販売しています。
世界市場でいうと簡単な機能だけがついている携帯電話を
買ってくれる人の方が数は多いからです。
2006年にノキアは南アフリカに進出しました。
まずは廉価版の販売に力をいれ、値段の安い携帯を売ることによって
世界シェアナンバーワンの座を不動のものにしています。
ではなぜ日本では廉価版を販売しないのか?という疑問がでてきます。
日本の携帯電話の特徴は
キャリアと呼ばれる移動通信会社(NTTやSBなど)による
独特の販売方法によります。
メーカーはキャリアの要望に応じて商品を生産
それが各キャリアのブランドごとに販売されています。
これまでキャリアは競うように、メーカに機能の向上を求めてきていました。
つまり、日本向けの商品をつくるのに精一杯で
海外向けの商品をつくる余力が会社としてないというのが
どこのメーカーも抱えている問題になっています。
しかしながら高性能を売りにしながら
世界的にシェアを拡大した会社が存在します。
さあ、それはどこでしょう?
そしてなぜでしょう?
その話は次回に・・・(引っぱりすぎですかねぇ~)
2008年03月05日
モノづくりの未来・・・1
日本の携帯電話の世帯普及率は90%近くになっている現在。
しかしながら、日本製携帯電話の世界的シェアが
2%にも満たない現状を皆さんは知っていますか?
最新の携帯をお持ちになっているのであれば、
ワンセグ対応、お財布ケイタイ(電子マネー)、テレビ電話、
指紋認証などができる多機能な機種になっています。
そう携帯一つがあれば生活できると言われるくらい
携帯の果たす役割が大きくなってきています。
ではなぜこの技術的にも優れた携帯が世界で売れていないのか?
なぜなのか???
答えは日本の携帯が高性能すぎるから・・・
そしてもう一つ世界市場へのグローバルな戦略ミスがあげられます。
最近のニュースでドコモのDシリーズを開発・生産していた
三菱電機が携帯電話の市場から撤退することを発表しました。
今度機種変更をするならDにしようかと考えていたので、結構ショックでした。
現在、Dを使っている方はもっとショックなのではないでしょうか。
さて、大手携帯メーカーの一つが撤退を決めた背景には
世界シェアが低いということも少なからず関連しています。
日本国内では携帯の端末は、爆発的なヒット商品でも出せない限り
すでにパイの取り合いもままならない状況です。
(それだけ大勢の人が携帯キャリアということ)
では、世界の携帯市場のシェアはどうなっているかというと
1位が ノキア (約38%) フィンランド製品
2位が サムスン (約15%) 韓国製品
3位が モトローラ (約13%) アメリカ製品
4位が ソニーエリクソン(約 9%) 日本・スウェーデン製品
5位が LG (約 8%) 韓国製品
残りのその他17%の中で2%弱が日本製
となっているのが現状です。
しかしながら海外メーカーの携帯電話を分解していくと・・・
スピーカー、カメラ、アンテナ、コンデンサーなど
その使われている部品の8割近くを日本のメーカーが占めているそうです。
海外製品であってもほとんどが日本製の部品で出来ています。
では、なぜ海外で日本の携帯が売れないのか?
実は日本の進んだ技術により売れなくなった原因の一端があるのです・・・
この続きはまた明日アップします。
しかしながら、日本製携帯電話の世界的シェアが
2%にも満たない現状を皆さんは知っていますか?
最新の携帯をお持ちになっているのであれば、
ワンセグ対応、お財布ケイタイ(電子マネー)、テレビ電話、
指紋認証などができる多機能な機種になっています。
そう携帯一つがあれば生活できると言われるくらい
携帯の果たす役割が大きくなってきています。
ではなぜこの技術的にも優れた携帯が世界で売れていないのか?
なぜなのか???
答えは日本の携帯が高性能すぎるから・・・
そしてもう一つ世界市場へのグローバルな戦略ミスがあげられます。
最近のニュースでドコモのDシリーズを開発・生産していた
三菱電機が携帯電話の市場から撤退することを発表しました。
今度機種変更をするならDにしようかと考えていたので、結構ショックでした。
現在、Dを使っている方はもっとショックなのではないでしょうか。
さて、大手携帯メーカーの一つが撤退を決めた背景には
世界シェアが低いということも少なからず関連しています。
日本国内では携帯の端末は、爆発的なヒット商品でも出せない限り
すでにパイの取り合いもままならない状況です。
(それだけ大勢の人が携帯キャリアということ)
では、世界の携帯市場のシェアはどうなっているかというと
1位が ノキア (約38%) フィンランド製品
2位が サムスン (約15%) 韓国製品
3位が モトローラ (約13%) アメリカ製品
4位が ソニーエリクソン(約 9%) 日本・スウェーデン製品
5位が LG (約 8%) 韓国製品
残りのその他17%の中で2%弱が日本製
となっているのが現状です。
しかしながら海外メーカーの携帯電話を分解していくと・・・
スピーカー、カメラ、アンテナ、コンデンサーなど
その使われている部品の8割近くを日本のメーカーが占めているそうです。
海外製品であってもほとんどが日本製の部品で出来ています。
では、なぜ海外で日本の携帯が売れないのか?
実は日本の進んだ技術により売れなくなった原因の一端があるのです・・・
この続きはまた明日アップします。
2008年02月27日
風が吹けば・・・桶屋が儲かる!?・・・2
今回は携帯電話会社が競争すると誰が喜ぶ?
ってことから意外な因果関係を考えてみます。
現在の携帯電話は薄いし軽いし、小型化への進化はすごいことになっている。
さて、この携帯電話の小型化によりとても喜んでいる人達がいます。
それは次の誰でしょう?
テレビ局? おもちゃ屋? 防犯グッズ? 電卓メーカー?
流れはこんな感じです。
まず携帯会社の競争が始まる。
(これは携帯が普及するにしたがって激化していますね。)
携帯電話が進化し小型化を目指す。
(10年前と比べると重さはかなり軽くなっています。)
小型の部品を開発する。
小型化された部品は大量生産され、生産コストが下がり安くなる。
部品を手直しして利用(ここがミソです。)
小型化された携帯電話の部品
(バイブレーションに使われている小型のモーター)を
手直しして利用し室内コントロール飛行機が作られている。
プロペラを回すローターの部分に携帯電話のバイブ機能用のものを
手直ししたものを使用。数年前までは約4千円だったものが
現在は100~200円で生産可能になった。
室内コントロール飛行機の値段は2500~4000円。
売り上げは70万個を記録。
室内コントロール飛行機の市場規模は現在30億円を超える。
つまり、おもちゃメーカーが喜ぶ
日本の生産技術は世界でも群を抜いて素晴らしいですね。
転んでもただでは起き上がらないというか・・・
発想の転換力が優れている。
しかしながら、最先端の技術力のあるにも拘らず
携帯電話の世界シェアをみると日本はかなり下位ランクに位置しています。
それはなぜか・・・
その話はまだ次回にでも。
ってことから意外な因果関係を考えてみます。
現在の携帯電話は薄いし軽いし、小型化への進化はすごいことになっている。
さて、この携帯電話の小型化によりとても喜んでいる人達がいます。
それは次の誰でしょう?
テレビ局? おもちゃ屋? 防犯グッズ? 電卓メーカー?
流れはこんな感じです。
まず携帯会社の競争が始まる。
(これは携帯が普及するにしたがって激化していますね。)
携帯電話が進化し小型化を目指す。
(10年前と比べると重さはかなり軽くなっています。)
小型の部品を開発する。
小型化された部品は大量生産され、生産コストが下がり安くなる。
部品を手直しして利用(ここがミソです。)
小型化された携帯電話の部品
(バイブレーションに使われている小型のモーター)を
手直しして利用し室内コントロール飛行機が作られている。
プロペラを回すローターの部分に携帯電話のバイブ機能用のものを
手直ししたものを使用。数年前までは約4千円だったものが
現在は100~200円で生産可能になった。
室内コントロール飛行機の値段は2500~4000円。
売り上げは70万個を記録。
室内コントロール飛行機の市場規模は現在30億円を超える。
つまり、おもちゃメーカーが喜ぶ
日本の生産技術は世界でも群を抜いて素晴らしいですね。
転んでもただでは起き上がらないというか・・・
発想の転換力が優れている。
しかしながら、最先端の技術力のあるにも拘らず
携帯電話の世界シェアをみると日本はかなり下位ランクに位置しています。
それはなぜか・・・
その話はまだ次回にでも。
2008年02月21日
風が吹けば・・・桶屋が儲かる!?・・・1
これは江戸時代に書かれた「東海道中膝栗毛」のなかでもでてくることわざ。
1.風が吹けば砂煙がまう。
2.砂煙がまうと、それが目に入って盲人が増える
3.盲人が増えると、三味線が売れる(当時、三味線は盲人が弾いた) 。
4.三味線が売れると、猫が減る。(三味線の皮は猫の皮を使用していたから)。
5.ネコが減ると、ネズミが増えて桶をかじる。
6.桶がかじられると、桶の注文が増えて桶屋が儲かる。
と、これは思わぬ事柄から始まったことが、
思わぬところに影響を及ぼすという例え話。
しかし現実の世界の中でも
いっけん何の関係もない事柄のように見えて
複雑に絡み合って経済が動いていることがあるそうです。
今年はオリンピックが開催されるのに、
年明けから冷凍餃子の問題で大変なことになっていますが、
「北京オリンピックが開催されると
日本のラーメン屋が困る!?」
という因果関係が・・・
それはなぜか?
まず
・北京オリンピック効果で、中国人が裕福になり、
コーヒーを飲む人が増える。
なんと北京オリンピックの経済効果は約15兆5000億円。
それに伴い中国人の給料は10年前と比べると2~3倍に増えている。
その結果、以前は家で1杯5円未満のお茶を飲んでいた人達が、
現在はカフェで1杯500円もするコーヒーを好んで飲んでいる。
中国のコーヒー生豆の消費量は2000年の1.6倍になっている。
だから
・コーヒー豆の需要が高まり、値段が上がる。
中国におけるコーヒー党の人が増えた。
結果、世界で品薄になりコーヒー豆の値段が上がる。
そして
・ベトナムでコーヒーに転作するコショウ農家が激増。
ベトナムはコショウの生産高世界1位であり、全世界の3割がベトナム産。
さらにコーヒーの生産高も1位にブラジルに次いで世界2位である。
コーヒーとコショウは栽培環境が似ているため転作が簡単。
しかもコーヒー作りの方が楽なので、
単価の高いコーヒーの方に転作する農家が増えた。
その結果コショウが不足して値段が急騰し、
1kg当たり2500円から2880円に15%も値上げされた。
あるラーメンチェーン店のコショウ代は年間28万8千円増になり、
ラーメン業界全体のコショウ代は年間1億800万円増になっている。
ゆえに
・コショウが品薄&値上げによりラーメン屋さんが困る
※ちなみにコショウは栽培が面倒なのでコーヒーからコショウ栽培に戻る農家はいないのだとか…。
1.風が吹けば砂煙がまう。
2.砂煙がまうと、それが目に入って盲人が増える
3.盲人が増えると、三味線が売れる(当時、三味線は盲人が弾いた) 。
4.三味線が売れると、猫が減る。(三味線の皮は猫の皮を使用していたから)。
5.ネコが減ると、ネズミが増えて桶をかじる。
6.桶がかじられると、桶の注文が増えて桶屋が儲かる。
と、これは思わぬ事柄から始まったことが、
思わぬところに影響を及ぼすという例え話。
しかし現実の世界の中でも
いっけん何の関係もない事柄のように見えて
複雑に絡み合って経済が動いていることがあるそうです。
今年はオリンピックが開催されるのに、
年明けから冷凍餃子の問題で大変なことになっていますが、
「北京オリンピックが開催されると
日本のラーメン屋が困る!?」
という因果関係が・・・
それはなぜか?
まず
・北京オリンピック効果で、中国人が裕福になり、
コーヒーを飲む人が増える。
なんと北京オリンピックの経済効果は約15兆5000億円。
それに伴い中国人の給料は10年前と比べると2~3倍に増えている。
その結果、以前は家で1杯5円未満のお茶を飲んでいた人達が、
現在はカフェで1杯500円もするコーヒーを好んで飲んでいる。
中国のコーヒー生豆の消費量は2000年の1.6倍になっている。
だから
・コーヒー豆の需要が高まり、値段が上がる。
中国におけるコーヒー党の人が増えた。
結果、世界で品薄になりコーヒー豆の値段が上がる。
そして
・ベトナムでコーヒーに転作するコショウ農家が激増。
ベトナムはコショウの生産高世界1位であり、全世界の3割がベトナム産。
さらにコーヒーの生産高も1位にブラジルに次いで世界2位である。
コーヒーとコショウは栽培環境が似ているため転作が簡単。
しかもコーヒー作りの方が楽なので、
単価の高いコーヒーの方に転作する農家が増えた。
その結果コショウが不足して値段が急騰し、
1kg当たり2500円から2880円に15%も値上げされた。
あるラーメンチェーン店のコショウ代は年間28万8千円増になり、
ラーメン業界全体のコショウ代は年間1億800万円増になっている。
ゆえに
・コショウが品薄&値上げによりラーメン屋さんが困る
※ちなみにコショウは栽培が面倒なのでコーヒーからコショウ栽培に戻る農家はいないのだとか…。
2007年03月04日
アイスブレイク
皆さんは、
「アイスブレイク」
という言葉を聞いたことがありますか?
英語で
break the ICE = 口を切って緊張をほぐす、打ち解ける
などの意味があります。
つまり、
氷の塊のようにガチガチに固まっている堅い雰囲気や、
相手の気持ちを和らげるようにできるツールのこと。
会議を行うときに、
皆がリラックスして発言しやすい雰囲気にするとか、
セミナーを始める場合に、
受講者の緊張をほぐしたりとか、
初対面の人たちの紹介時に、
お互いをよりよく知り合うためだったりとか、
様々な目的に応じて、使うことのできるツールの一つです。
セミナーや会議でも
テーマの前に別の話題で頭をはたらかせて、
口を開いたり、あるいは体を使ったりすることによって
リラックスして本テーマに取り組む準備ができるようになるんですね。
「アイスブレイク」
は全員参加型のゲームやクイズが
一般的で誰でも使えるツールだったりします。
しかし使い方には気をつけなければいけない場合もあるのでご注意を。
まぁ、
初対面の方が多いセミナーであれば、
セミナー参加者の紹介をゲームでする
というのも効果的なアイスブレイクでしょうね。
きたる
3月10日開催の
ファシリテーション基礎講座 講師の大塚真実氏は
アイスブレイク講座の
オリジナルDVDを発売されているので、
アイスブレイクに興味がある方もぜひ、
講座への参加をお待ちしています。
「アイスブレイク」
という言葉を聞いたことがありますか?
英語で
break the ICE = 口を切って緊張をほぐす、打ち解ける
などの意味があります。
つまり、
氷の塊のようにガチガチに固まっている堅い雰囲気や、
相手の気持ちを和らげるようにできるツールのこと。
会議を行うときに、
皆がリラックスして発言しやすい雰囲気にするとか、
セミナーを始める場合に、
受講者の緊張をほぐしたりとか、
初対面の人たちの紹介時に、
お互いをよりよく知り合うためだったりとか、
様々な目的に応じて、使うことのできるツールの一つです。
セミナーや会議でも
テーマの前に別の話題で頭をはたらかせて、
口を開いたり、あるいは体を使ったりすることによって
リラックスして本テーマに取り組む準備ができるようになるんですね。
「アイスブレイク」
は全員参加型のゲームやクイズが
一般的で誰でも使えるツールだったりします。
しかし使い方には気をつけなければいけない場合もあるのでご注意を。
まぁ、
初対面の方が多いセミナーであれば、
セミナー参加者の紹介をゲームでする
というのも効果的なアイスブレイクでしょうね。
きたる
3月10日開催の
ファシリテーション基礎講座 講師の大塚真実氏は
アイスブレイク講座の
オリジナルDVDを発売されているので、
アイスブレイクに興味がある方もぜひ、
講座への参加をお待ちしています。